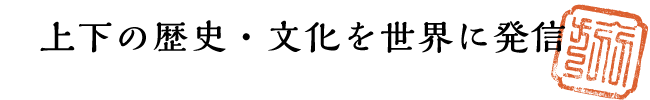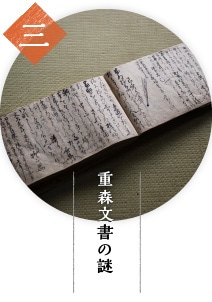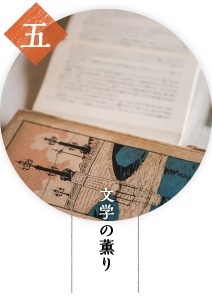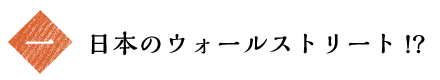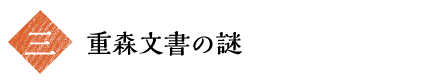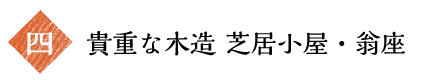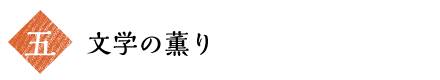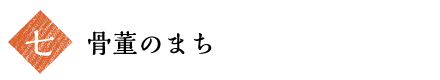「天領」とは、江戸時代における江戸幕府の直轄領のこと。正式には「御料・御領」「御料所」「代官所」など。徳川幕府が軍事的、経済的に重要であると認めた土地を直接治めた領地のことで、代官所や郡代役所、陣屋(出張陣屋)などが置かれ、管理されていました。当時の主要都市であった長崎や大坂、佐渡金山のあった佐渡、湯の花から明礬を生産していた明礬温泉なども天領とされていました。
江戸時代、土地は皇室領や天領、寺社領、大名領などに分かれていました。勝海舟編『吹塵録』所収「天保十三年全国石高内訳」によれば、江戸時代後期の天領は、総石高の14%にあたる420万石を占めたとされています。